「画像生成AIに興味があるけれど、何だか難しそう…」
「お金を払う前に、まずは無料でどこまでできるのか試してみたい」
もしあなたが今、このようにお考えなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。この記事は、専門的な知識がなくても、今日から画像生成AIを安全に、そして楽しく始められるように作られた、初心者のための入門ガイドです。
無料で使えるおすすめのツールから、初めての画像生成で失敗しないための簡単なコツまで、わかりやすく解説していきます。
もし、この記事を読み進める中で「AIを自社の宣伝・広告課題の解決に活用したい」「社内向けにAI活用の勉強会を開催したい」と感じられたなら、私たちがお力になれるかもしれません。まずはお気軽に、記事の末尾かお問い合わせからご相談ください。
そもそも画像生成AIとは?3分でわかる基本の仕組み

最近よく耳にするけれど、一体「画像生成AI」とは何なのでしょうか。この技術は、まるで魔法のように思えるかもしれませんが、実はとても理論的な仕組みで動いています。その基本を知ることで、AIへの漠然としたな不安が解消され、より安心して活用できるようになります。ここでは、難しい専門用語は使わずに、AIが絵を描くイメージを3分で掴めるように解説します。
結論から言うと、画像生成AIとは「膨大な数の画像と、それに対応する説明文を学習し、新しい指示(テキスト)に基づいて、学習した内容を応用して全く新しい画像を作り出すプログラム」のことです。
なぜなら、AI自身は人間のように「犬」や「空」が何であるかを本当に理解しているわけではないからです。AIは、「犬」という言葉と共に学習した何百万枚もの犬の画像から、画素(ピクセル)単位で「犬らしさ」のパターンを統計的に覚えています。そして、「犬の画像を作って」と指示されると、その膨大な記憶の中から統計的に最もそれらしい画素の組み合わせを再構築して、新しい犬の画像を作り出すのです。
例えば、私たちが「リンゴ」の絵を描くとき、頭の中にある数え切れないほどの「リンゴの記憶(色、形、光沢など)」を頼りに、見たことのない新しいリンゴの絵を描きますよね。AIが行っているのは、これと非常に似た過程です。その記憶の量が人間とは比較にならないほど膨大で、描くスピードが圧倒的に速い、とイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
つまり、画像生成AIは「超高性能な記憶力を持つ、絵の描き方を学習したプログラム」と考えることができます。この基本さえ押さえておけば、AIに対する見方が変わり、次のステップへ進む準備が整います。ルごとの表現傾向に大きな違いを生む要因となります。
どこまでできる?無料で使える画像生成AIの「できること」と「制限」

「無料で試せるのは分かったけれど、実際どこまでのことができるの?」多くの方がそう思われることでしょう。無料プランには確かにいくつかの制限がありますが、それでもなお、あなたの日常業務や個人の創作活動を豊かにする、驚くほど多くのことが可能です。その一方で、ビジネスで本格的に使う際には注意すべき点も存在します。ここでは、無料で「できること」の具体的な可能性と、知っておくべき「制限」について、分かりやすく解説します。
無料プランで「できること」の具体的な例
無料の画像生成AIは個人的な利用や、ビジネスにおける資料作成などの補助的な役割において、大きな効果を発揮します。
なぜなら、現在の無料ツールは、数年前の有料ツールに匹敵するほどの性能を持っており、簡単な指示で見栄えの良い画像を瞬時に生成できるからです。これにより、これまでデザインに費やしていた時間やコストを大幅に削減し、本来の業務に集中することが可能になります。
例えば、あなたがブログ記事を書いているとします。「オーガニック野菜」というキーワードに合う挿絵が必要になったとき、AIに指示すれば、数秒で新鮮な野菜のイラストや写真を複数パターン生成してくれます。同様に、社内向けのプレゼンテーション資料で「未来の都市」というスライドに添えるイメージ画像や、SNSで注目を集めるための投稿用画像なども、専門知識なしで手軽に作成できるのです。
このように、無料プランはアイデアを手軽に視覚化し、日々の業務や創作の質とスピードを向上させるための、とても有用なアシスタントとなります。
無料プランの主な「制限」について
その一方で、無料プランには「生成回数」「商用利用」「機能」の3つの観点で、ビジネスでの本格利用においては無視できない制限が存在することを理解しておく必要があります。
ツール提供会社にとって、無料プランはあくまで多くの人に技術を体験してもらうための「お試し版」という位置付けだからです。そのため、サーバーに負荷のかかる大量生成を制限したり、より高度な機能やビジネス利用の権利を有料プランの特典とすることで、収益化を図っています。
具体的には、多くの無料プランでは1日に生成できる画像の枚数に上限が設けられています。また、生成した画像にツールのロゴ(ウォーターマーク)が強制的に入ったり、利用規約で広告などの営利目的での使用が制限されていたりする場合があります。さらに、生成画像のサイズを大きくする高解像度化機能や、他のユーザーに作品を見られないようにする非公開設定といった、ビジネスで重要となる機能は有料プラン限定となっていることがほとんどです。
したがって、無料プランはあくまでAIの能力を試し、個人的な範囲で活用するためのものと捉え、ビジネスで継続的かつ本格的に利用する際には、有料プランへの移行を検討するのが賢明な判断と言えるでしょう。
初心者におすすめ!無料で始められる画像生成AIツール3選

「無料でできることは分かったけど、ツールがたくさんありすぎて、どれから試せばいいか分からない…」画像生成AIの世界へ第一歩を踏み出す際、誰もがこの壁にぶつかります。複雑なツールを選んでしまい、難しさに挫折してしまうのは非常にもったいないことです。
そこでこの記事では、AI技術をリードする3大企業(Adobe, OpenAI, Google)が提供する、初心者向けの代表的な無料ツールを厳選しました。それぞれのツールの特徴の違いに触れながら、AIの世界を安心して体験してみてください。
Adobe Firefly ― クリエイターの味方、「安心感」で選ぶなら
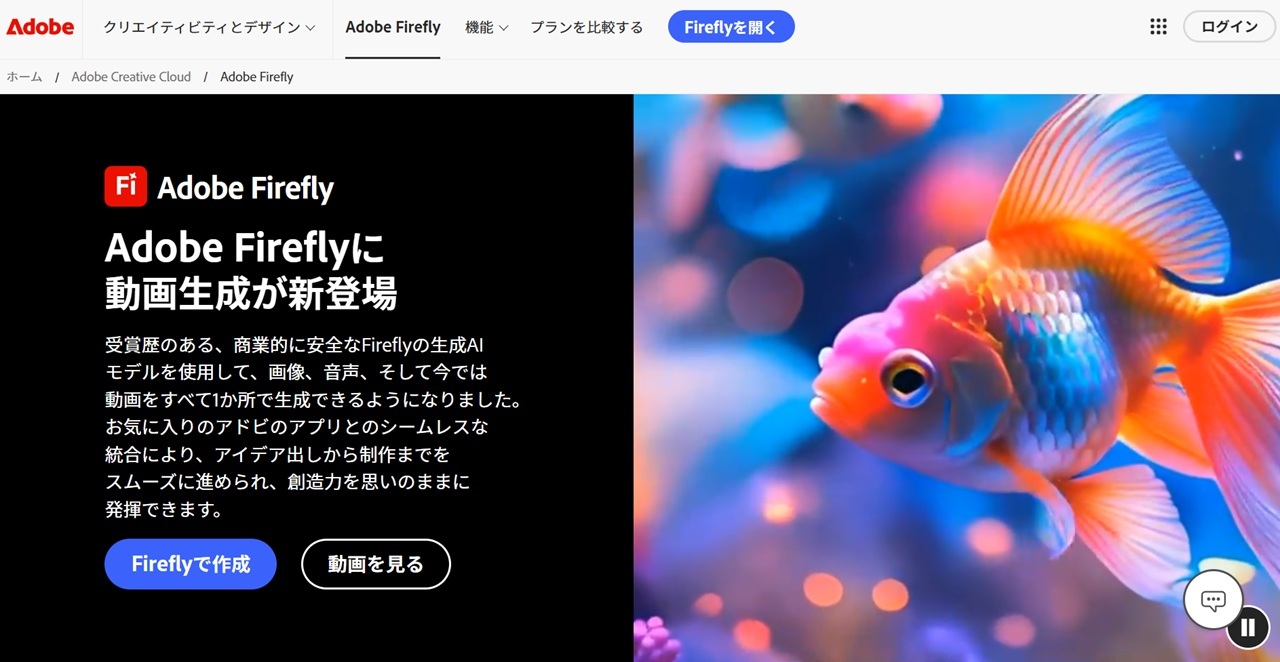
「ビジネスでの利用も少し考えているので、著作権的に安全なツールから始めたい」という方に最もおすすめなのがAdobe Fireflyです。クリエイティブ業界の標準ツールを提供するAdobeならではの、信頼性の高さが最大の魅力です。
Fireflyは学習データにAdobe Stockの画像など、権利的にクリーンなものが使われているため、「商用利用の安全性」が高いと公式に発表されているからです。月に25回まで無料で画像を生成でき、生成した画像にはAdobeのロゴ(透かし)が入りますが、その品質と安全性を無料で体験できるのは大きなメリットです。
例えば、企業のブログ記事で使う挿絵を試しに作ってみたい、といった場合に最適です。Photoshopなどの同社製品との連携も強力なため、将来的に本格的なクリエイティブ制作へステップアップしていくことを見据えた「最初のツール」として、非常にバランスが取れています。
このように、Adobe Fireflyは「安全な環境で、高品質な画像生成を体験してみたい」という初心者にとって、最も信頼できる選択肢の一つです。
ChatGPT ― 誰もが知るAIとの「対話」で始める

ChatGPTは、「とにかく今すぐ、最も簡単な方法で画像を生成してみたい」という方に最適なツールです。普段使っているLINEのように、自然な日本語でAIと対話するだけで画像が生まれる手軽さは、他の追随を許しません。
このツールは、OpenAIが開発した最新の言語AI(GPT-4o)に、画像生成AI(DALL-E 3)が組み込まれたものです。そのため、ユーザーは画像生成のための特別な画面や設定を覚える必要が一切ありません。ただチャット画面で「〇〇の画像を作って」と話しかけるだけです。
具体的には、「笑顔の柴犬のリアルな写真」や「アニメイラスト風の夏の田舎の風景」といった文章を入力するだけで、すぐに複数の画像候補が生成されます。「もう少し犬を左に寄せて」といった追加の要望にも応えてくれるため、AIと対話しながらイメージを具体化していく面白さを最も手軽に体験できます。
無料プランでは、1日の画像生成回数に制限があります。目安として1日3回といわれています。
したがって、ChatGPTは「AIとの自然な対話」を通じて、画像生成の基本的な楽しさを知るための入口となります。
Whisk ― アイデアを「リミックス」する、新しい発想のツール

Whiskは、「テキストで指示するのは苦手だけど、面白いアイデアを視覚的に探求してみたい」という方に最適な、Googleが提供する実験的なプラットフォームです。Googleアカウントでログインして利用することができます。
このツールの最大の特徴は、テキストだけでなく、「主題」「場面」「スタイル」の3つの参考画像を組み合わせることで、全く新しいビジュアルを「リミックス」できる点にあります。言葉にしにくい細かいニュアンスを、画像でAIに伝えるという新しいアプローチを体験できます。
例えば、「自分のペットの写真(主題)」と「SF映画のポスター(場面)」、「水彩画のイラスト(スタイル)」を組み合わせることで、思いもよらないユニークなアート作品が生まれるかもしれません。新しいアイデアの源泉を探したり、創造的な遊びを楽しんだりするのに最適なツールです。
よって、Whiskは「AIを創造的なブレインストーミングのパートナーとして使ってみたい」という好奇心旺盛な初心者にとって、最高の遊び場であり、新しい発想を得るためのツールとなります。
初めてのプロンプト作成:3つのコツだけでOK!
さあ、使ってみたいツールは決まりましたか?次に挑戦するのは、AIへの「指示文(プロンプト)」作りです。これがAIイラスト作成で最も面白い部分であり、同時に多くの初心者が「何をどう書けばいいの?」と悩むポイントでもあります。しかし、安心してください。初めから完璧な指示文を書く必要は全くありません。たった3つの簡単なコツを意識するだけで、AIはあなたのイメージを理解し、驚くような絵を描いてくれます。ここでは、誰でもすぐに実践できるプロンプト作成の秘訣をご紹介します。
コツ1:「具体的」に伝える
最も重要なコツは曖昧な言葉を避け、具体的な言葉で伝えることです。
なぜなら、AIは人間と違って「いい感じの絵」といった、ふんわりとしたイメージを理解するのが苦手だからです。「良い/悪い」の判断基準を持たないAIには、「何が」「どこで」「何をしている」といった具体的な情報を一つひとつ教えてあげる必要があります。
例えば、「きれいな猫」と指示するだけでは、AIは何を描いていいか迷ってしまいます。そうではなく、「公園のベンチの上で、毛づくろいをしている、茶色くてふわふわな子猫」のように、具体的な情景を描写してあげることが、良い結果への一番の近道です。
したがって、AIとの対話では「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を少し意識して、具体的な情報を付け加えてあげるのが基本となります。
コツ2:短い言葉を「組み合わせる」
次に意識すべきは、完璧な長文を一気に書こうとせず、短いキーワードをカンマ(,)で区切って組み合わせるという考え方です。
これは、AIがテキストを単語やフレーズ単位で理解しているためです。文章として少し不自然でも、AIに伝えたい要素(パーツ)を単語で並べていく方が、かえって意図が正確に伝わることが多くあります。
例えば、「夕暮れの海辺で犬と散歩している写真」を生成したい場合、文章で長く書く代わりに「一人の女性、犬と散歩、夕暮れのビーチ、金色の光、波、フォトリアル」のように、描いてほしい要素をパーツとして分解し、並べてみましょう。こうすることで、AIは各要素を設計図の部品のように扱い、より的確に画像を組み立ててくれます。
つまり、初めは完璧な文章を目指さず、描いてほしいモノや雰囲気を表す「単語のリスト」を作る感覚で始めるのが、プロンプト作成を簡単にする秘訣です。
コツ3:「英語」で伝える
最後に、もし可能であれば簡単な英語で指示を出すと、より高品質な画像が生成されやすい、ということも覚えておきましょう。
なぜなら、現在AIの学習に使われている画像やテキストの大部分が英語だからです。そのため、日本語で指示するよりも、英語で指示した方が、AIが持つ膨大な知識をより正確に、そして深く引き出すことができます。
最新のAIは日本語も非常にうまく理解してくれます。しかし、例えば「水彩画風」と指示するよりも「watercolor painting」と英語で指示した方が、より多彩で本格的な画風のイラストが出てくる可能性が高まります。DeepLやGoogle翻訳といった無料の翻訳ツールを使えば十分なので、恐れる必要は全くありません。
したがって、日本語で試してみて、「もっと本格的な絵が見たいな」と感じたら、そのプロンプトを翻訳ツールで英語にしてみる、というのが、初心者から一歩先に進むための効果的なテクニックです。
もっと詳しく知りたい方へ:次のステップのご案内

画像生成AIの基本を体験してみて、「もっと色々なツールを試したくなった」「ビジネスでの本格的な活用方法も知りたくなった」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。AIの世界は非常に奥深く、あなたの好奇心に応える、さらに専門的な情報がたくさん存在します。しかし、いきなり専門的な記事を読むと、情報量が多すぎて混乱してしまうこともあります。そこで、あなたの次のステップとして、目的別に最適な2つのガイドをご用意しました。
各ツールの「実力」や「作風の違い」を比較したい方へ
主要なAIツールの性能や、同じ指示でどのような絵を描き分けるのかに興味が湧いた方には、私たちの「実践・比較ガイド」が次のステップとして最適です。
なぜなら、この記事では今回ご紹介したツールを含め、主要な画像生成AIに全く同じ指示(プロンプト)を与え、その出力結果を横並びで詳しく比較・分析しているからです。
例えば、「人物写真」「製品広告」「アニメ風イラスト」といった、ビジネスでよく使われるテーマで、各ツールがどのような強みや個性を持っているのかを、実際の生成画像と共に具体的に知ることができます。
したがって、このガイドはツールの「個性」を深く理解し、あなたの目的に合ったツールを見つけるための、より専門的な羅針盤となります。
→【画像生成AIツール比較】主要6サービスを同一プロンプトで試す
ビジネスでの「商用利用」や「料金」を詳しく知りたい方へ
もしあなたが、「生成した画像を広告や商品に使いたい」「法人契約できる料金プランを知りたい」と考えているなら、私たちの「商用利用比較記事」がその疑問にお答えします。
この記事は、ビジネス利用を検討する企業担当者の方々に向け、各ツールの料金プラン、そして最も重要である「商用利用の条件」や「著作権」に関する利用規約を、一つひとつ丁寧に調査・分析しているからです。
具体的には、「Midjourneyを大企業が使う際の特別な料金プラン」や「Canva AIで生成した画像を公開する際の必須条件」など、安全にビジネス活用するために欠かせない、専門的な情報を網羅しています。
よって、この記事はAIを趣味の範囲から一歩進め、ビジネスで本格的に活用することを検討し始めたあなたにとって、必読のガイドです。
→【2025年最新】画像生成AIのおすすめ6選|料金・商用利用を制作会社が徹底比較
まとめ
本記事では、画像生成AIの基本から、無料で使えるおすすめのツール、そして初心者でも失敗しないプロンプトのコツまでを解説しました。画像生成AIはもはや専門家だけのものではなく、誰もが気軽に始められる、創造性を拡張するための強力なパートナーです。
なぜなら、専門知識がなくても直感的に操作できるツールが数多く登場し、無料で試せる環境が整っているからです。
この記事で紹介したツールの中から、一番「面白そう」だと感じたものに触れてみてください。そして、簡単なコツを参考に、あなたの頭の中にあるイメージを言葉にしてAIに伝えてみましょう。きっと、想像を超える驚きと楽しさが、そこに待っているはずです。
まずは気軽に遊んでみることが上達への一番の近道です。この記事が、あなたの創造的なAI活用の、安全で楽しい第一歩となれば幸いです。
本記事は2025年7月時点の情報に基づいて作成されています。生成AI技術は日々進化していますので、最新の情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
ブルーアールに相談してみませんか?
「AIを活用して自社のプロモーション課題を解決したい」
「社内向けにAI活用の勉強会を開催したい」
このようにお考えの方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。貴社の課題に寄り添い、最適なクリエイティブをご提案します。
▼制作実績はこちら
https://blue-r.co.jp/works/
▼サービス一覧はこちら
https://blue-r.co.jp/service/






